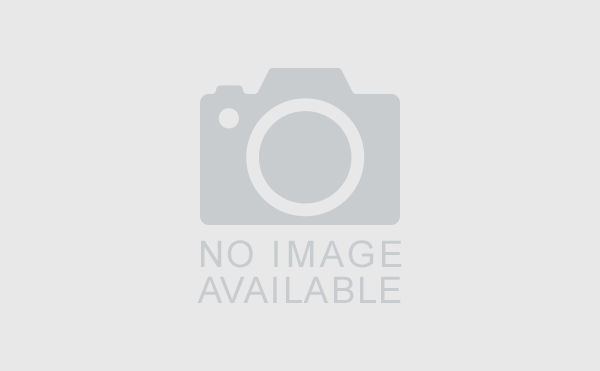やり抜く力「グリット」とは?
新学期にはいりましたね。娘はようやく小学3年生になりました。
3月末生まれで、おそらく、クラスでは一番誕生日を迎えるのが最後で、入学当初は学校の授業や活動についていけるだろうかと心配しておりましたが、おかげさまで、親の心配をよそに、好奇心旺盛で、日々新しい環境を前向きに楽しんでいる様子です。さて、そんな娘は、年長の夏ごろから、ピアノを習っています。娘は幼児期から歌が大好きで、音楽がいつも身近にあって、気張らず長く続けてほしいという思いで始めることにしました。去年は、発表会に向けての練習が嫌で、一度は辞めると言っていた時期もありましたが、何とかここまでやってきました。今年はぐっと難易度の上がった課題曲にチャレンジすることになり、ゆっくりすぎるほど譜読みに時間がかかっていたので、難しいようであれば、少し端折って編曲しようかという先生の提案もありましたが、マイペースながらに、原曲のまま弾けるようになりました。(まだまだつっかえてばかりですが)そんな娘の様子を見ていて、思い出した言葉があります。
「グリット」です。
グリット(grit)とは、「やり抜く力」または「粘る力」だと定義されている言葉で、心理学者でペンシルバニア大学教授のアンジェラ・リー・ダックワース氏が提唱しました。
彼女は「才能やIQ(知能指数)や学歴ではなく、個人のやり抜く力こそが、社会的に成功を収める最も重要な要素である」と提言しています。
◎グリットを構成する4つの要素
グリットは、以下の4つの要素が必要だとされており、各々の頭文字を取ってGRIT(グリット)と呼んでいます。
①Guts(度胸):困難なことに立ち向かう
②Resilience(復元力):失敗しても諦めずに続ける
③Initiative(自発性):自分で目標を見据える
④Tenacity(執念):最後までやり遂げる
このグリットを伸ばす、育てる方法は様々あるようですが、私が刺さったのは、以下3つ。
- より少し難しいことに挑戦する
- 成功体験を積み上げる
- 短期だけでなく長期目標を視野に入れる
普段できることを続けていても、グリットは育たないので、自分のスキルより少し上の目標を設定していく必要があります。
まずは「無理」という先入観を持たず、「もしかしたら、できるんじゃないか」「どうやったらできるだろうか」と、物事を前向きに捉える癖をつけていく。
グリットの高い人は、多くの失敗を経ています。失敗したとしても、めげずに挑戦し続けることが重要です。
また、急に大きなことに挑戦すると、やり抜く前に心が折れてしまいます。そうならないために小さいことでも成功体験を積み上げ、自己肯定感を高める必要があります。
グリットは子供たちの人格形成にたいへん良い影響を与えると私は思っています。これが達成できたのだから、次はもっと難しいことにチャレンジしてみようというモチベーションを呼び起こしてくれるきっかけとして、普段のレッスンでも、子育てにおいても、グリッドを意識していけたらと思っています。